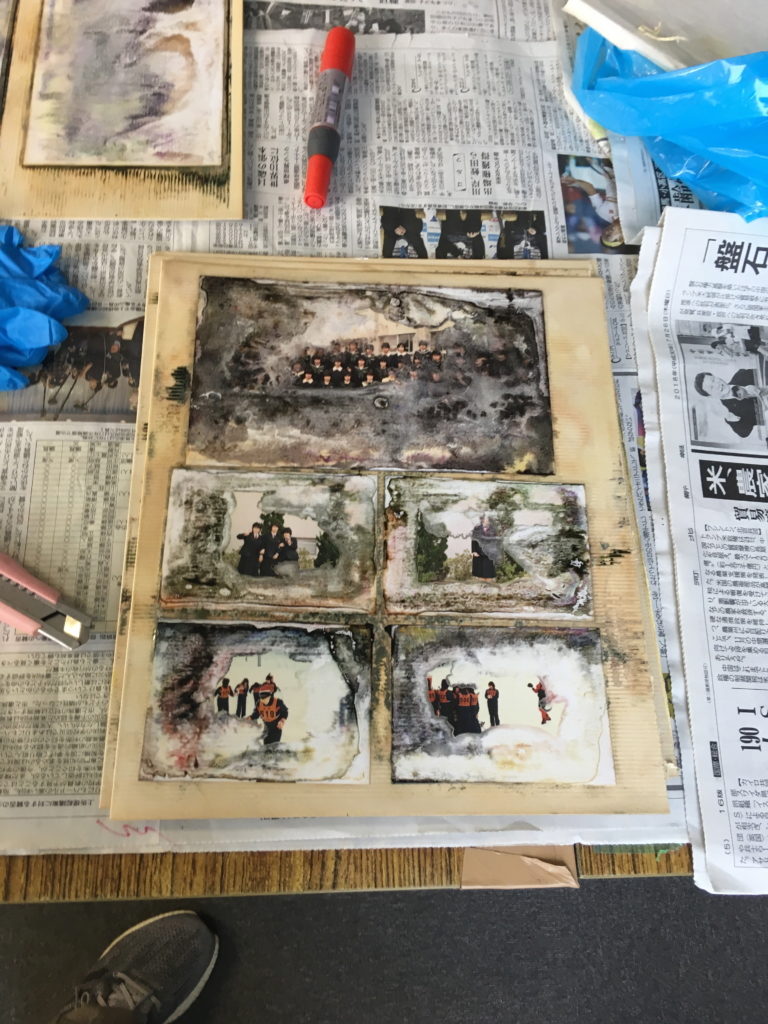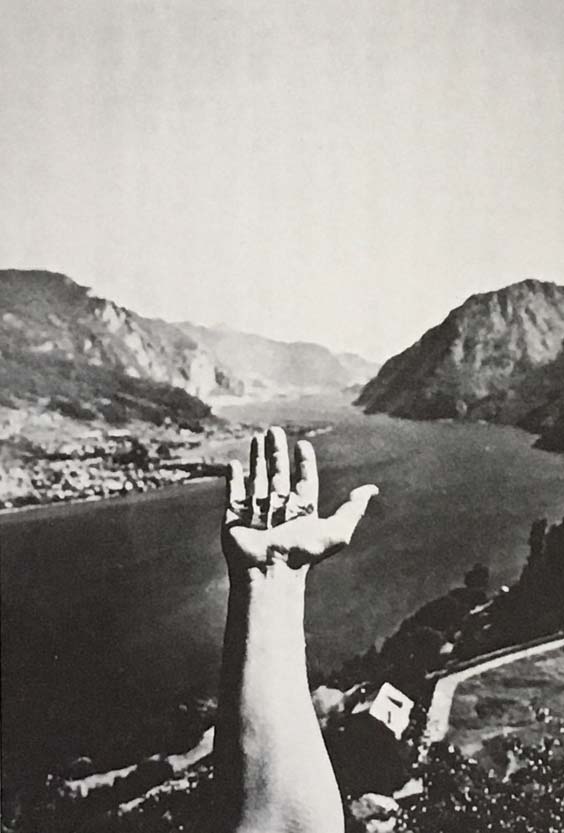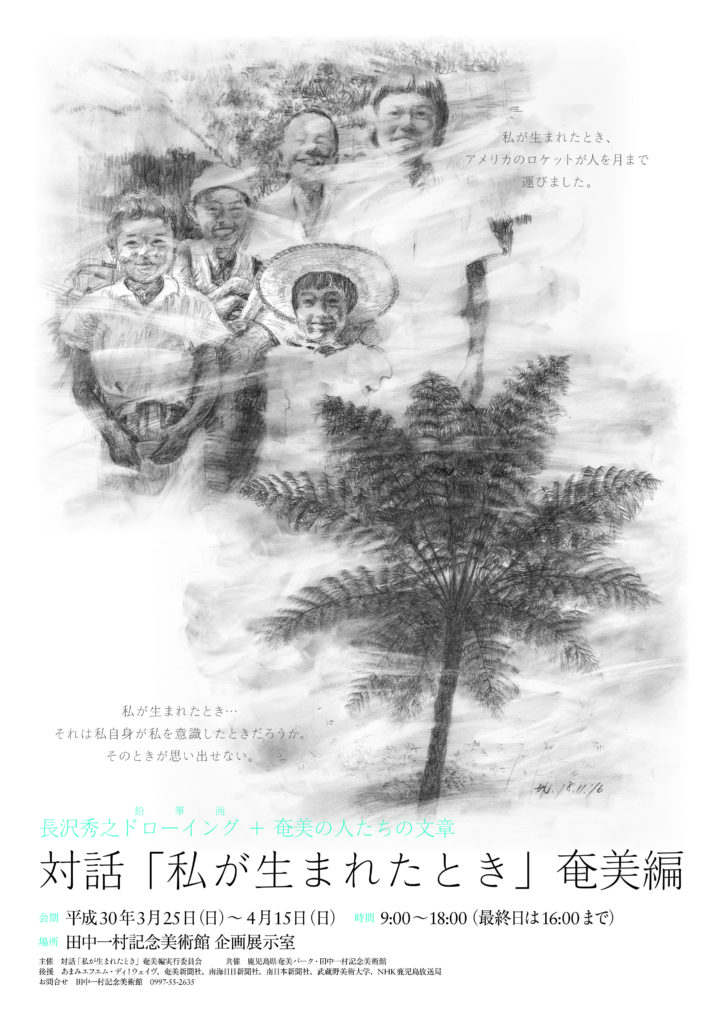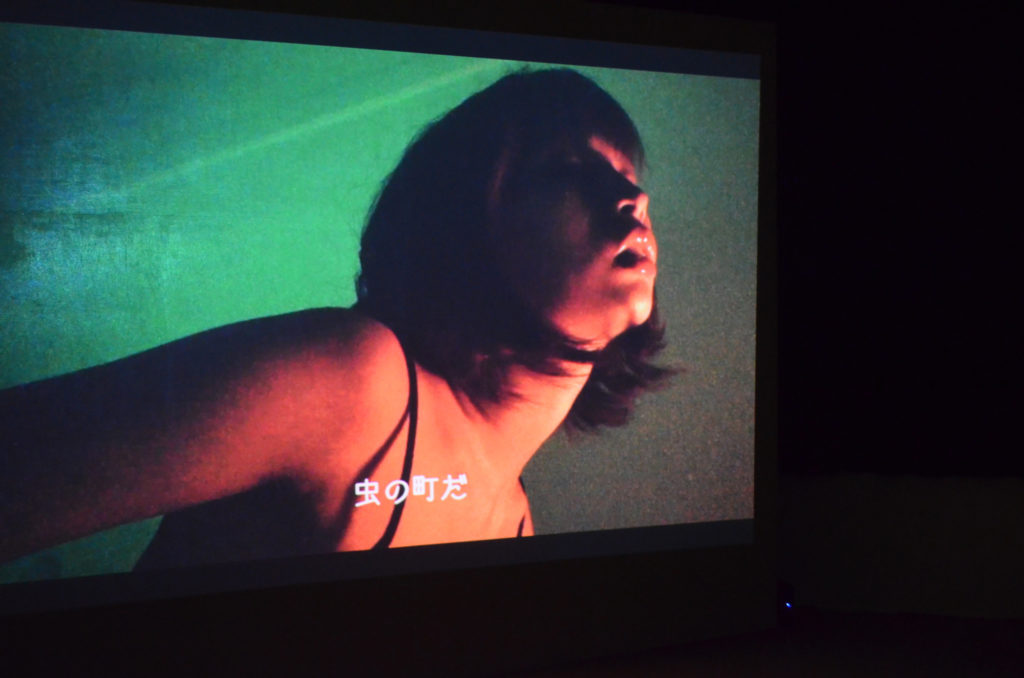TRANS- グレゴール・シュナイダー <<美術館の終焉−12の道行き>>を見る
アートはどこかで現実にコミットしていなければ生きのびていけない。だから今、アートは極めてむずかしい立場に立っている。趣味の世界の「アート」は相変わらずもてはやされているが、括弧のないアートが成立するのはここ日本ではむずかしい。 ところが奇跡のようにここでアートが成立している現場を見た。神戸TRANS−展でのグレゴール・シュナイダーの<<美術館の終焉−12の道行き>>と題された展覧会。全部で12箇所の展示があり、それぞ…