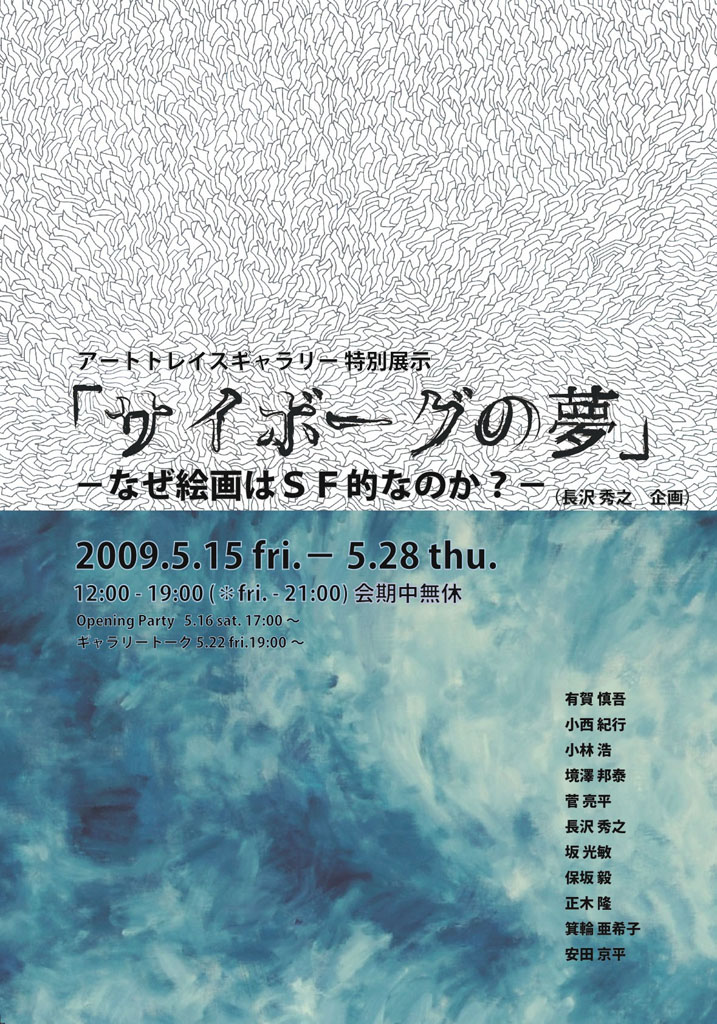「いつの頃から身体がなくなってしまったのか記憶にないんだけど、つくづく身体がないなと思ったんですね。」(押井守)
パソコンやケータイのディスプレイを通じて、視覚はCPUにつながり、そこに集積された欲望はさらに無数のCPUを通じて変形され、個々の視覚と脳に配 給される。感覚の延長は当然のごとくそれらによって統合されている身体や自意識にまで変化をおよぼす。それらの視覚を中心とした圧倒的な情報量の前に、触 覚はかたすみに追いやられている。
否、正確を記すならば、現代にあっては、視覚や触覚を中心としたもろもろの感覚は分断されている、と言うべきなのだろう。感覚を統合して出来上がる「リ アル」はもうすでになく、私たちは分断された感覚を並べながら現実の海を泳いでいる。触覚を失った透明な視覚だけの世界や視覚を失った者が描く世界像、そ んなものに近い感覚のありようだ。そこでは実際の空間やそのスケール感覚も変質してしまい、世界は“計量できる空間”から測ることのできない全く別の空間 になっている。
中心に住まうはずの神もなく、人間もなく、そこにいるのはサイボーグのみ。そんな状況が今、生まれつつあるのではなかろうか。しかし、私たちは完全なサ イボーグではなく、いわば中途半端なサイボーグである。完全なサイボーグが“電気羊の夢を見る” としたら、当然のごとく、人間はほんものの羊の夢を見るのだろう。そして中途半端にサイボーグ化した私たちはほんものの羊でも電気羊でもない“中途半端な 羊”の夢を見るしかないのだ。
それは精密な機械では起こりようのない“誤作動”のようなものである。サイボーグと化した人間が現実をとらえ直し、自分にかすかに残された身体感覚から それを取り込もうとする時に感じる違和感、そこから広がる不安と希望に満ちた予想外の感覚こそが、この“誤作動”の正体である。“誤作動”とはしかし深い 意味で脳の再調整(リセット)であって、修復でもある。つまり、夢とはそういったものかもしれない。
“中途半端な羊”は、“誤作動”によって、リアルとアンリアルの間を行き来する中で生まれる。
それはまさに私たちが、絵を描くなか、そっちの世界(絵のなかの世界)と、こちらの世界(現実の世界)を行き来するときに生じるものにほかならないので はないだろうか。“中途半端な羊”とは絵をつくるひとがキャンバス上に見るものの別称なのだ。
絵をつくる行為は、必然的にサイボーグの夢のようなものにならざるを得ず、その意味でSF的である。
一般にSF(サイエンス・フィクション)は、現実の次元の不可能性を超えて、別の次元の可能性をさし示す。そしてフィクションでありながら、現実よりも リアルになりうる要素をもっている。それと同じように、絵画行為もまた虚構がリアルになる可能性をはらんでいる。その一方で私たちが、いかにゆがんだ空間 のなかに生きているのかを露呈させ、いかにこわれやすいイメージに囲まれているのかを暗示する。両者はともに現実の次元をくぐり抜けようとしているのだ。
といっても、絵画はSFを説明するわけでもないし、SFが絵画の説明になるわけでもない。絵画は、誤作動が誘発する“中途半端な羊”の夢を見る限りにお いてSF的なのだ。実際の制作と夢が違うように、身体や物質が絡んだもの(絵画)と、フィクションとはその“場所のありか”が違っている。前者は“場所” を必要とし、後者はそれを必要としない。SFの透明性に比べ、絵画はあまりにも多くの不透明性をかかえこんでいる。(場所は、現実空間、身体、物質等々を 含む)両者の違いはあきらかである。
にもかかわらず、なぜ絵画はSF的なのか?
私たちには“危機が迫っている”。人間から追いやられ、完全なサイボーグからもまた追いやられている。その危機のなかで、私たちはたとえば一方で身体を 必要とし、他方でそれを不要とするのではないだろうか。(そういう状況に追い込まれている)
現実と想像世界をつるりと自由に行き来するためには身体はいらないだろう。次元を移動し、脳をトリップするにはそれは不要なのだ。しかし、私がいる“こ こ”を意識するには身体が必要だ。そうやって、こことあそこを行き来するなかで、私たちは“イメージ”を獲得するのではないだろうか。それがはたして何の 役にたつかわからないが、それは私たちに必要なものではある。想像力とは、もともと次元移動できないものが持つ“特殊移動技術”のようなものである。その “技術”が生む“誤作動”と、それによって生まれる“中途半端な羊”という“イメージ”を必要とするのは、実は私たちの側なのだ。
それは、私たち自身が、中途半端な羊の夢を見る、誤作動に満ちた存在であるからにほかならない。これはシニシズムではなく可能性の問題である。
私たちは完全な存在になろうとしているのでもなく、全き感覚の回復を企てようとしているのでもない。もはやそれはありえないのだ。むしろ誤作動に満ちた 存在、いや存在でもない、誤作動に満ちたサイボーグであることを肯定しようとしている。
私たちは、サイボーグの夢を見る。SFのように絵画をつくる。地球から遠く離れたこの地球という星で・・・。
以下、「サイボーグの夢」とはどのようなものなのか。個々の作品を通してそれを見ていきたい。
坂の超微細絵画はもうひとつの視覚の迷宮である。フラットランドの生き物が3次元を見られないかの如く、それは強固な線だけの世界だが、どうしてもそこ になにか別のものがひそんでいることを示してしまう。それはなんなのか?
管のクラシックな小型室内画。そこに住まう生き物は小さいのか、大きいのか。あるいはもういなくなったのか。それともこれはイメージの製造工場のようなものなのか。すべてが謎である。
同じように、正木の「くつ」もまた頭でつくられたイメージを彷佛させる。用途を忘れたかたちだけのもの。それは宇宙人が見た私たちの日用品の姿であり、とどのつまり私たちのなまの姿でもある。
境澤のフォーマリスティックな絵画は、零度の絵画と読むことが可能である。視界も感覚もない、およそ物語なぞどこにもなく、なにごとも始まらない零度の 部屋のアナロジー。しかしそこには無数の手の痕跡がつまっている。その集積こそ、物語以前の原イメージにほかならない。
保坂の絵画は、宇宙の窓である。マチスの絵画が窓をひんぱんに描いたように、彼もまたミニマルな窓をつくる。ただしその窓から見えるのは庭の風景ではな い、視線をはね返す無の光景だ。それはまるでこちらの姿を映さない鏡のごとく存在する。
安田の「昇天図」は宇宙版のイコン図にほかならない。聖母の昇天は宗教的というよりは、一種の空間のマ二エリズムであり、そこが現実と通じているところ だ。超絶技巧の歪んだ空間のなかでの祈りとはいかなるものなのだろう?
小西の描く“身近な”人間たちは、もう退化してしまったのだろうか?それともこれらは進化のかたちなのだろうか?いずれにしても、それは人間よりも“生き物”に近い。いや、ようやく、生き物になったと言うべきか。
小林の“無重力絵画”は時間感覚をかく乱する。ものすごいスピードで私たちは生きているのかもしれないし、とんでもない遅さで生きているのかもしれない・・。恐るべき暴力性と、静止から生まれるユーモア。
有賀の装置は息苦しさと解放を同時にめざす。それはまるで自らのサイボーグとしての限界を試し、鍛練しているようにも見える。何のためか?彼は無謀にも 絵のなか(宇宙、死)とこちら(地球、生)の両方を同時に生きようとしている。
箕輪(特別参加)の「ウルトラマン」は、わたしたちの「ウルトラマン」という認識をリセットする。しかし、そのときのリセットする主体は必ずしも、人間 とは限らない。動物かもしれないし、異星からの来訪者かもしれない。それらにとっての“ウルトラマン”とはしかし何なのだろう?
註1.「ユリイカ」特集:押井守 2004年4月号の上野俊哉との対談から
この中で上野の「身体を捨てられないから人形にこだわるんですかね。」という問いに対し、押井は「逆に身体がないからなんだと思う。」と答え、本文中の ことばを発言している。ちなみにこの後の発言は「そうすると、なぜ自分が人形が好きなのか、犬と暮らしたいのか、街について考え続けてきたのかということ がわかってきた。戦車とか軍艦にしても全部僕にとっての身体だった。それは僕だけじゃなくて、人間にとってみんなそうだったんじゃないかと思えてきた。」 と続く。
2.サイボーグとはサイバネティック・オーガニズムの略。人間には生存不可能な環境<海底、宇宙空間、異星上>での活動を可能にするために内蔵や手足な ど、頭脳以外を人工に改造強化したもので、あくまで元は人間であるところが、アンドロイドとは異なる。ちなみにアンドロイドとは行動、外見、思考などが人 間そっくりのロボットのこと。(横田順弥著、「SF大辞典」から引用)
3.フィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」を参照。
主人公のリック・デッカードが、賞金稼ぎ(バウンティハンター)となって火星から逃亡した6人のアンドロイドを追いつめて殺す(廃棄処理する)物語。
地球は放射能の灰に汚染され、異星への植民計画が進んでいる。ここでは生きている動物を飼うことが最高の欲望となっていて、主人公も電気羊を飼っている が、本物の動物を飼いたいとつねに思っている。リックはフォークト=カンプフ感情移入度検査法という一種の感情移入度を測る測定法をたよりにつぎつぎとア ンドロイドを追いつめていくが、彼らを殺すことにも疑問を感じていく。
フィリップ・K・ディックは人間とアンドロイドの識別を描きながら、その判別の難しさ、わけても人間とは一体なんなのか?という問題を提示しているよう に思う。著者がこの物語を書いたのは1968年。時代設定ははっきりとはわからないが、「ネクサス6型脳ユニット」がでたのは1991年となっているか ら、ちょうど今か、もう少し以前のことなのだろうか?いずれにしても現在のところ、物語中にあるような有機ロボットも空中を飛ぶホバー・カーも発明されて はいない。しかし2009年に生きるわたしたちから見れば、人間の“アンドロイド性”(この文で言うならばサイボーグ度)は十分進んでしまったように思わ れる。ではそのとき、何を根拠に存在を“人間”というのか?その問いは今も有効である。
4.ここで言うサイボーグとはこの定義から少しずれるかもしれない。“元は人間”というところは合致しているが、“頭脳以外”というところは合っていな い。“元は人間であるが、環境の改造によって頭脳や感覚までも変わってしまったもの”がここでの新しい(?)定義。
5.SFは広い意味での科学を主題とした小説であるが、科学的仮説をもとにしたものにとどまらず、仮説から自由になり、非科学のほうへ、時に、より荒唐無 稽に向かおうとする傾向さえ感じられる。現実の摂理よりは未知のカオスへと向かうその根底には、未来への夢や逃避があるかもしれないが、それよりももっと 切実な現実感覚の危機意識がある。その意味では、どんなにはるかな“宇宙旅行”も内面への旅にならざるを得ず、“ロボット”や“アンドロイド”“サイボー グ”の物語もこの地球に生きる者について語ることにならざるをえない。