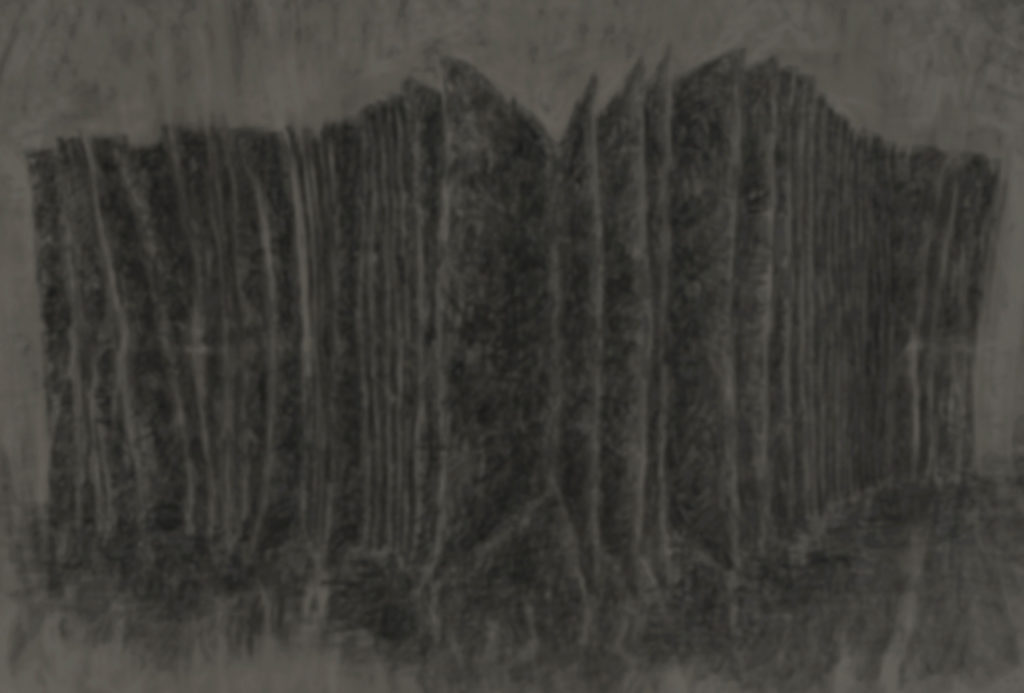百年あとの記憶 11.3.2111
100年もの時間が過ぎ去った。その間、さまざまなできごとや災害が起こったが、なかでも忘れることのできないできごとは2011年3月11日に起こった大津波による大川小学校の小学生らの死と、2019年、20年から世界的な感染爆発が続いたコロナウイルス禍である。
できごとの記憶をたどるために、おれたちはまた塔のある場所に行った。ひときわ大きな2011の塔。そのまわりを多くの死者が取り囲んでいた。やがて死者たちは無言のままゆっくりと歩きだし、塔の周りを回り、なかには塔のなかに入ったり出たりするものもいた。ある感情がおこるとそれはさながらさざ波のように他の人に伝わっていき、うねりとなり大きな波となった。その様子を見ていると、ひとりの少年がやってきて、水でぐっしょり濡れた本を差し出した。それはアルバムと日記を混ぜたようなもので、本というよりは手綴じの紙の束のような体裁だった。ぼろぼろになったその頁をめくると、水やドロで半分消えたような子どもの写真やその子らが遊んでいる写真があり、そこには不鮮明な説明らしきことばもあった。
先生、山さ上がっぺ。
なんで山に逃げないの?
ここにいたら地割れして地面の底に落ちていく。
おれたち、ここにいたら死ぬべや!*
*彼女(生存児童)によると、学校から再び出てきた遠藤教諭は「山だ!山だ!山に逃げろ!」と叫んだという。その警告に呼応するようにふたりの少年も6年生の担任の佐々木先生にこう訴えて、裏山のほうに向かって駆け出したという。しかし遠藤先生の意見は却下され、ふたりの少年たちも戻って静かにするように命じられた。(「津波の霊たち 3.11 死と生の物語」リチャード・ロイド・バリー著からの引用による)
小学生74人とその先生10人が津波にのまれて一挙に亡くなった事件は、不可解なうえになんともやりきれない感情を残すが、このリチャード・ロイド・パリーのレポートによれば、そのときの避難場所がはじめは決まっていたものではないことを示している。
校庭に集合した際に、ある児童は裏山に逃げることを先生に提案した。
ひとり生き残り、後の裁判で出廷できる精神状態にないと主張し続けた遠藤先生も当初は山に逃げることを叫んでいる。教頭先生も山に逃げることを提案はしているのだが、地元の区長は、ここまで津波が来ることはないと言って三角地帯へ行くことを主張した。そして最終的にそこに避難することが決まる。すでに津波が来ることは、ラジオの警報や市職員の広報車による放送で地区のひとたちに伝わっていた。
ある児童の母は津波警報を聞き、その高さが段々高くなるのを知り、担任の佐々木先生に「津波が来るから山に逃げて」と大きな声で告げている。そのときの先生の言葉。
「お母さん、落ち着いてください」(前掲書よりの引用)
このことをロイド・バリーは“佐々木先生の根拠のない自信”と書いている。
そうなのだ。本を読んでいてやりきれない気持ちになるのは、こういうことなのだ。警報などから今までにない大きな津波が来ることがわかっていながら、組織の上にたつ大人たちは、危機を感じていない。そればかりか感覚的に危険を感じる子どもの言うことを聞かずに“今までのやり方”をマニュアルとしてやろうとする。そして招いた悲劇は間違いなく天災ではなく人災なのだが、その責任もうやむやになる。責任を問う裁判でさえも時間がかかり、それ自体が批判されたりするのだ。
前掲書は言う。「問題は津波ではない。日本が問題だった」
そしてこれは2019年か始まったCOVID-19のときも同じようなことが繰り返された。“自粛”ということばは政治が成立していない状況と、責任を取らない指導体制を象徴することばだった。この国はことばを首相自らが徹底的に破壊した。政治が人びとの信頼のもとに成り立っていることを軽んじたから、いざ危機を迎えたときにことばが通用しない。信頼があれば強い法的措置も考えられたが、それもなくただただ曖昧な“自粛”にたよらざるを得なかった。それでも国民は礼儀正しく、我慢強く、ほとんど服従のようにこれを守り災害が通り過ぎるのを待った。一国の指導者が、危機のときに生殺予奪の権利を持ってしまうことを見せつけられながら、その政策を批判するひとは数十%ぐらいしかいなかったのである。
弱い立場にある人がものを言い、それが全体にいかされなかったら、政治はないものといってよい。子どもの言うことやお母さんが訴えること、エラくなくても少数派でもそのひとの言うことに耳を傾けなければならない。
100年もの月日が流れるなかで、人びとはこのことを反省し、「平等に言える法」なるものをつくった。これは基本的人権などを言う場合の理念的な平等ではなくてもっと具体的な平等を指した。学校や大学では教員と学生が平等とされ、一方的な教育は廃止された。小学校では先生が教壇に立って生徒がみんなそれに向かう(服従する)かたちも廃止され、机はランダムに配置された。議会も議員構成は男女半数づつとなり、会社もそれにならった。それによって多くの人の声が平等に扱われ、エラいひとの声が他を圧するようなことはなくなった。いままで思われていた不都合は意外にも何でもないものとして乗り越えられたが、権威や権力を保持したいひとたちは陰湿な抵抗を繰り返した。
思えばCOVID-19の感染爆発のあった時代は異常であった。ゾンビのような権力者がオリンピックの責任者にしがみつき、“復興”という名の五輪大会を主張したが、これも延期のうえに最終的には中止になった。
曲ったことばを発する元首相が「民度が違う」というとんでもない誤解の言を平然として吐いていた。指導者たちがまず狂っていたから、その人たちが他者を救ったり、思いを寄せたりすることはまず不可能に近かった。それでも多くのひとが我慢した。政治的に異を唱えずに我慢した。これもまた狂っていた。
我慢し過ぎである。我慢すると政治家は怠惰になり、無責任、無能になる。
この国ではまた不思議なことばが蔓延した。
「がんばろう」とか「自己責任」とか「自粛」がそれである。それはひとりひとりの声に耳を傾けないかけ声であった。権威からのかけ声で、基本的には指導者の責任逃れの仕組みの一環であった。ただその改革にはことばが必要だった。壊れたことばを組み立てなおすには何十年と言う月日が必要で、その前にまずだれもがおかしいと思ったことを発することが必須だった。
しかし災害や天災は時を待たない。この百年は地球変動のときとして記録されるだろうがそれは次の千年、万年単位の変動のほんの些細な前触れにすぎなかった。