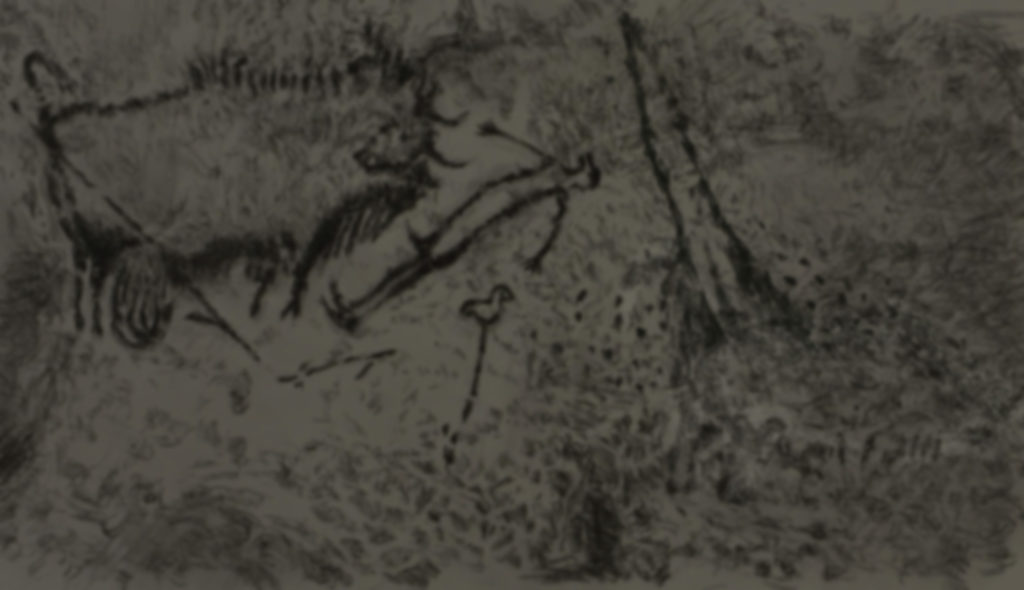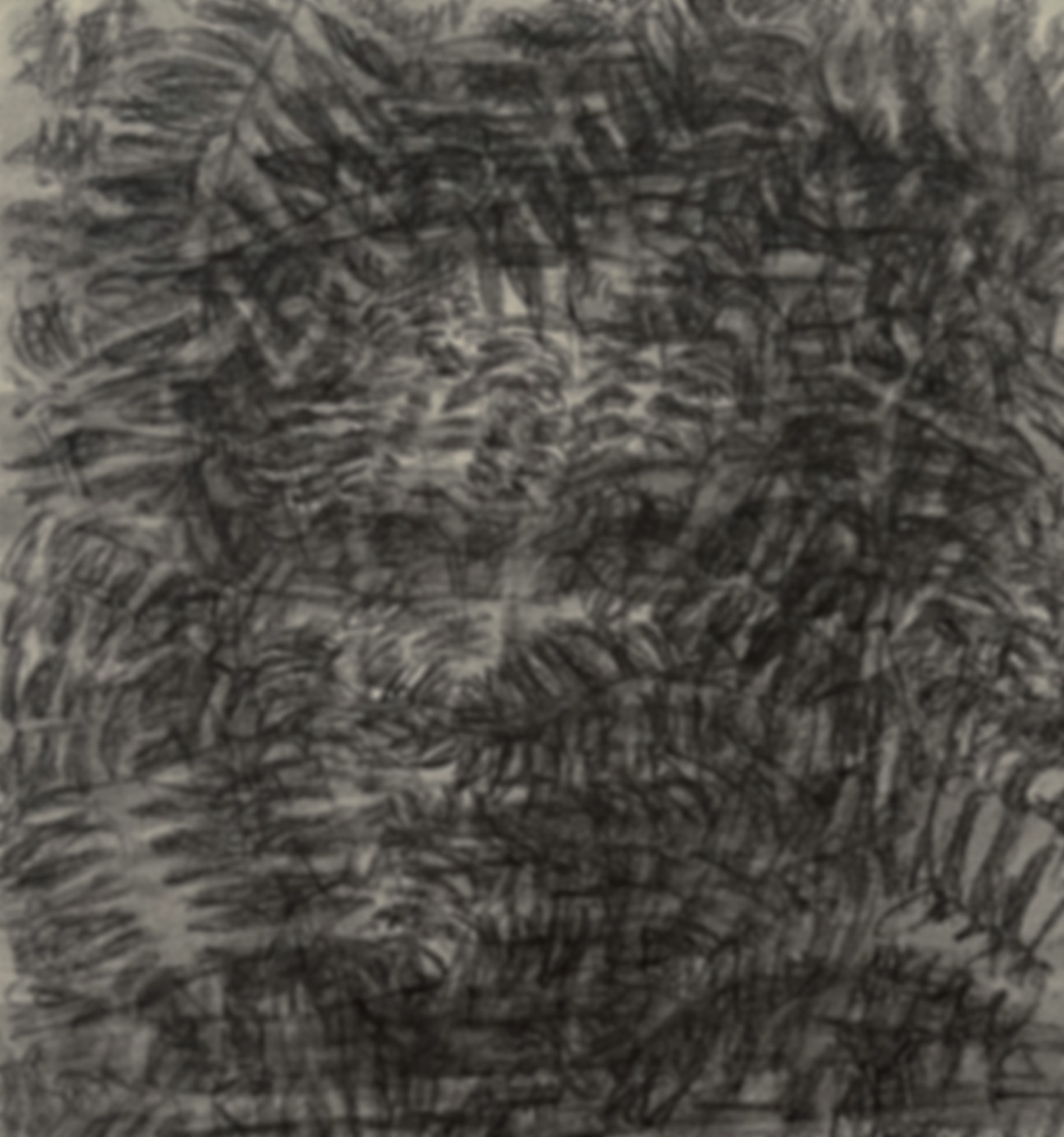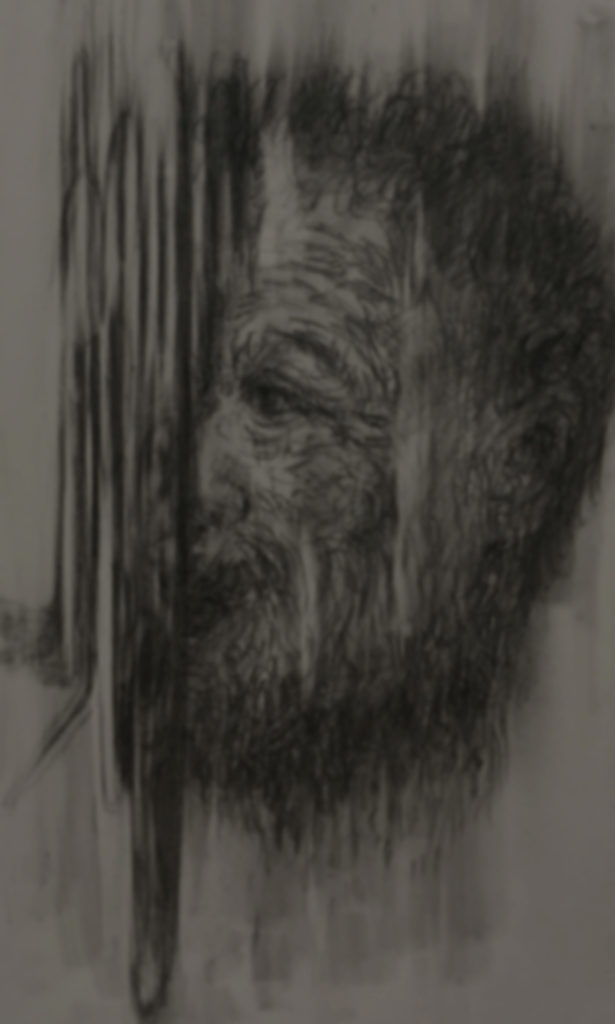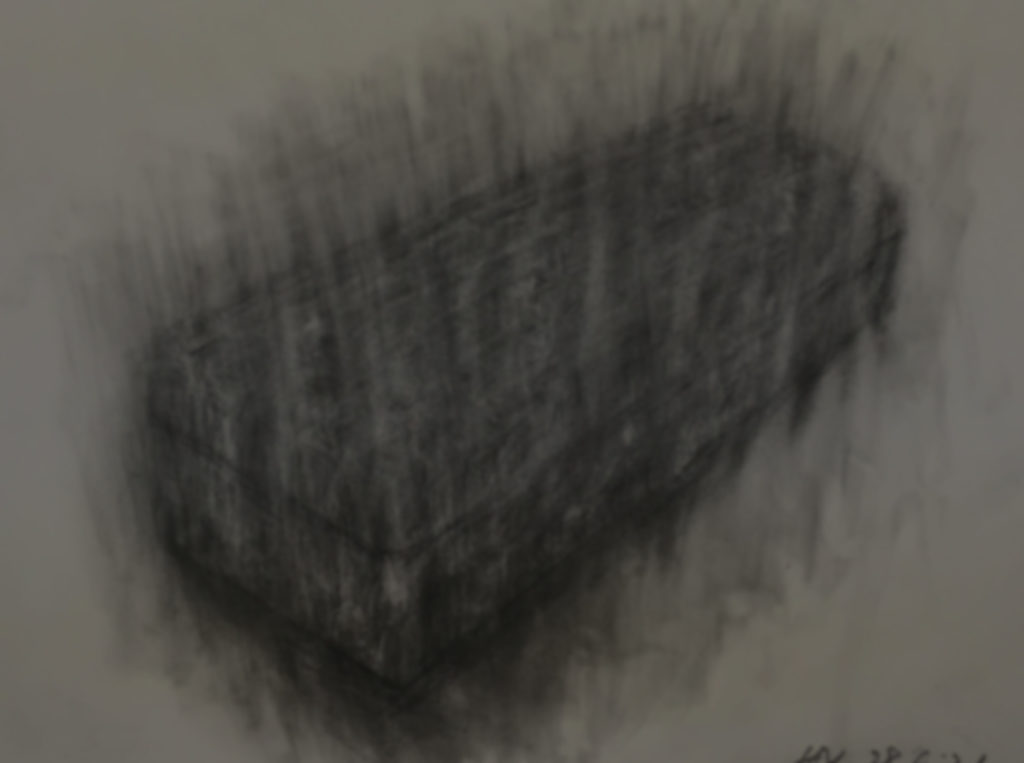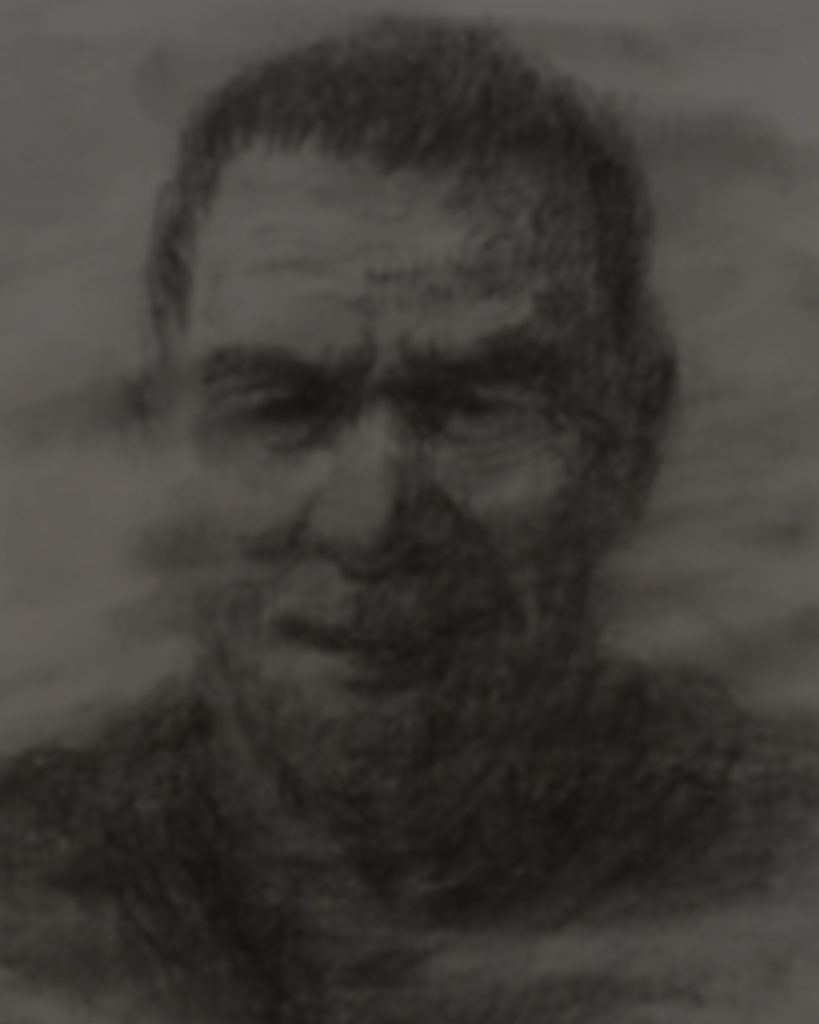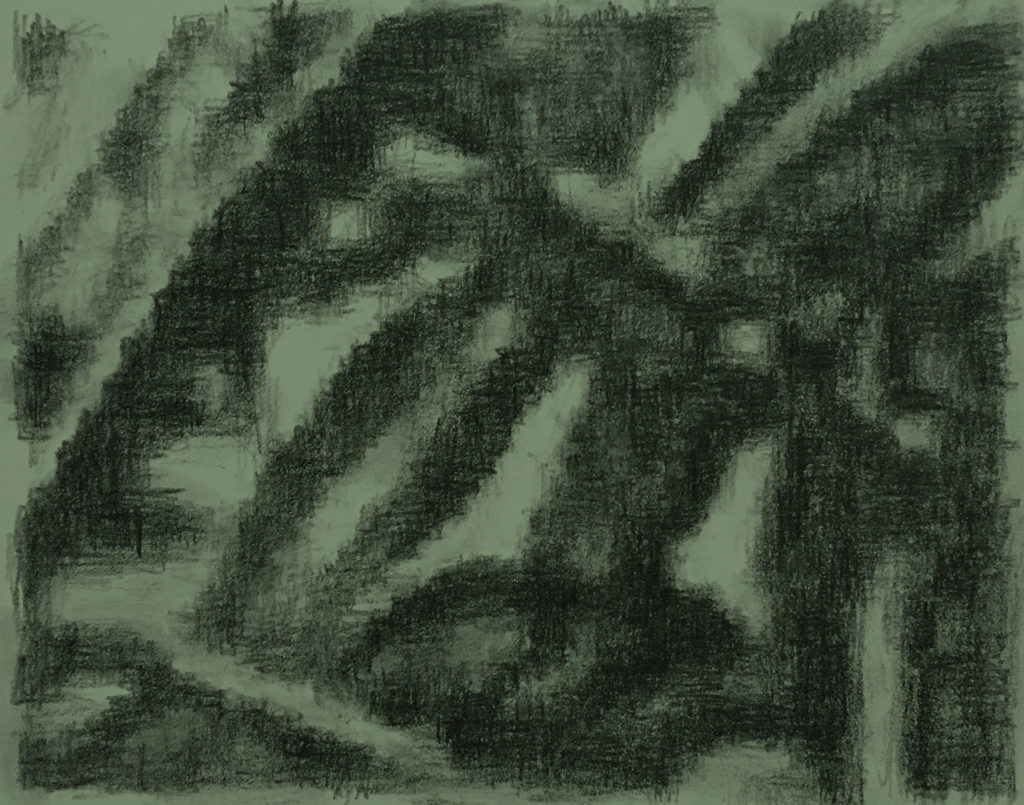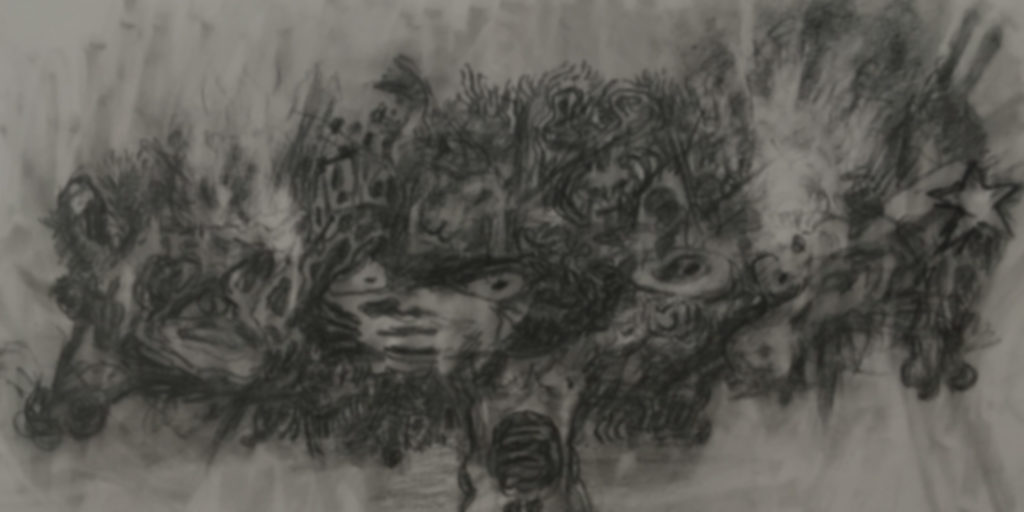C通信61. 思考は光速よりも速し Thoughts travel faster than light
オレたちが零下40度もあるひとウサギの部屋に到達したのは2020年の4月のことであった(C通信11.回廊)それからあっという間に時間が過ぎ去り、すべてのひとが老いた。 ひとウサギのことば「ここは死者のこたつです。オマエらはここには入れない。なぜならばボディーを持っていないからだ。早く出て行け!」はまだ解けない。 植物だけがアンテナを張って成長し、不死の街は静まり返っている。 思考は高速よりも早い。現実にはありえない光年のかなたに、老いた者がたどりつくことがある。加えてその者…