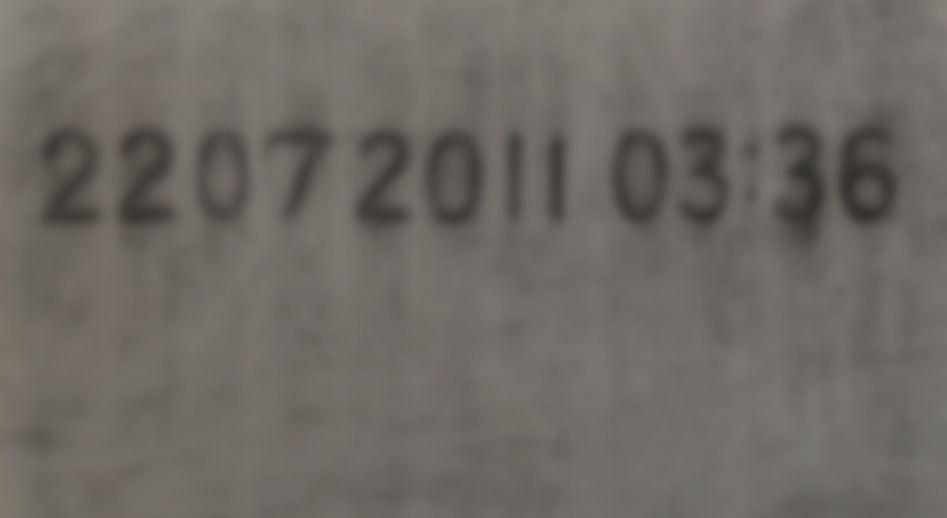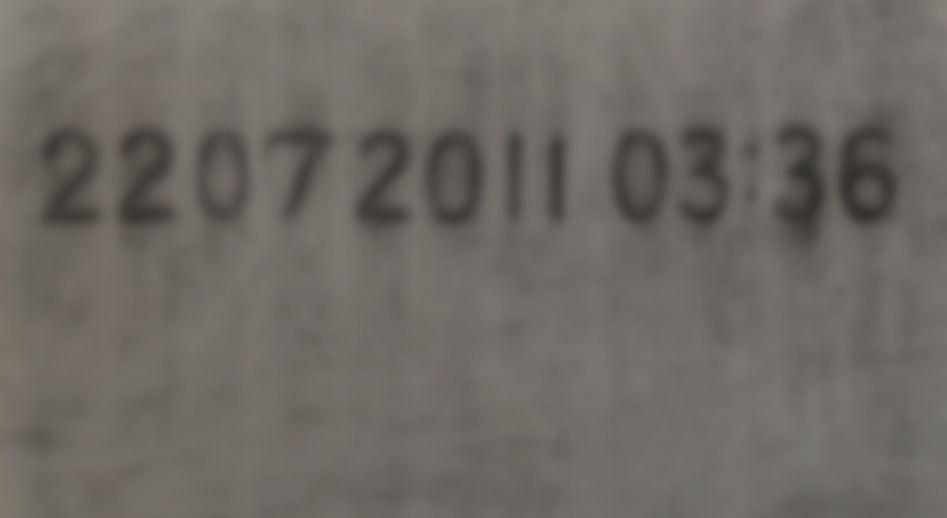書きものの束。おれはそのなかのひとつを引き抜いた。そのおもてには
22 07 2011 03:36
という数字が刻印され、そこに次のようなことが書かれていた。
母が死んだ。2011年7月22日の午前3時36分だった。
前日の21日午前中に転院先のO医師から「すぐ来て欲しい」という電話があった。C市のクリニックに到着すると、もう妹夫婦はそこに着いていた。パーキンソン病で地元のA病院に入院したのを皮切りに、さらに特殊疾患病棟のある隣町のB病院に転院。そしてここは3つ目にたどりついたクリニックであった。
O先生の話を聞く。
「リスクはある。しかしB病院のT先生から“この人をなんとかしてやって欲しい”と頼まれたことや、今朝のカズさんの状態、意識がしっかりしているその表情を見て、直感的に決めました」と言う。そして腸の写真を見せながら、それがパンパンに詰まってしまっていること、このまま放っておけば、時間を待たずに死にいたってしまうことが先生の口から説明された。一刻の猶予も許されない。そのなかで危険ではあるけれど、可能性もあるのでそれに賭けてみたい、そういうことを言っていた。断片的ではあるが、その時言われたことをさらに書きつけると次のようになる。
「ことばは悪いがイチかバチです。可能性に賭けてみます」
「このまま放っておいても、腸が全く詰まって動かない状態だから、患者さんを大変な苦しみのなかに置いておくことになる」
「普通だったらこのお年の患者さんには、ここで手術はしないですよ。放っておいて死を待つということです」
19日に妹夫婦が聞いた限りでは、リスクが大きすぎて手術は無理、ということだった。兄弟全員も母本人も、手術はしないという方針で決まっていた。とくに母は「手術はいや」と、はっきり言っていた。だから手術のことを聞かされた時には私たちも戸惑った。しかし先生もこの短い期間のうちに、リスクを背負った可能性に賭けてみようと重大な決断をしたに違いなかった。私はその決断の方向に少し傾いていた。
家族で話し合い、その日の12時頃までに決断して欲しいとのこと。その承諾がもらえれば、午後4時には手術ができるということであった。医院を出て近くにあったファミレスに入り、妹夫婦と私の3人で協議する。妹夫婦も同じ意見で、そのあとすぐに弟たちに連絡して同意を取り付けた。それをすぐさまクリニックに告げ、軽い食事をしてクリニックに着いたのは午後2時ちょっと前だった。
母の鼻には管が通されていた。その前日の20日には看護師がいくら試みても通らなかったものだ。全体に痛々しかった。
目は見開き、口も開けっ放しで、恐怖の表情は否定しがたかったが、意識だけはしっかりしていた。おなかの全体が張っていてそこが痛い、苦しいと言う。妹と一緒になって話しかけたり、手をさすったりしていると、外の林からうぐいすの鳴き声がしてきた。
ホー ケキュケキュ……ホーホケキョ…
しばらくしてまた
ケキョ ケキョ……ホーホケキョ……
「母さん、うぐいすが鳴いているよ、ほら、聞こえる?」と私が聞く。
しばらく沈黙がつづき、母の目だけがぎょろっとうごく。母が言った。
「それどころじゃないよ…」
それを聞いて、そこにいたみんながどっと笑い、母も笑った。
和歌を詠み、自然の変化に人一倍敏感であった母が、今は生死の重大な局面にぶつかり「それどころじゃないよ…」と言う。たしかにそうだ、こんなときにうぐいすと言われても。
そこには、“息子たちはこんな時にのんきだなあ、でも生きていくというのはそれでいいんだ。自分は死んでいくのだから、お前たちの関心事にはつきあっていられない、こっちは時間がないんだから…”そういう意味もあっただろう。それをユーモアに包んでひと言で言ったのだ。
母は死に際してことばがさえていた。このことばはそのなかでも忘れがたいものだった。
妹からもらった時計もはずそうとしなかった。寝たきりの状態から時計を見て、世の中の進行を周りに告げてみんなを笑わせていた。B病院から救急車で搬送されて来たときも母は時計を見て「40分かかったからここは千葉のほうに来てしまったの?」と聞いた。「ここは隣のとなりの町だから」と言っても「みんなダマされているんだよ」と真剣に言い疑っていた。そして何回ものやりとりのなかでようやく納得した。
B病院のときは、私は週に2回、母の元を訪れたが、この時のうれしそうな顔も忘れられないものだった。私はとんでもない錯覚にとらわれた。
母が自分の子どものような気がして来たのだ。親と子の関係が逆転しまい、母はあどけない子どものようになり、甘えるように何でもよく話した。窓から見える山の景色を見ながら「しっかり見ておくの」などとさかんに言った。生きているうちにしっかり見ておくのか、それとも景色とともに飛来する数々の思いがあったのか。東日本大震災のこともテレビで知って驚いていた。「大変なことになった、大変なことになった…」とつぶやいていたが、自分の身に起こっているできごともそれに劣らず大変だった。
いざ手術となると、それを拒否している母に、そのことをどう告げるかという問題があった。手術のためにレントゲン室に入り、裸にされてレントゲン写真を撮ったのだが、その際になにかの手違いがあったらしく、母は病室にもどるなり「ごめんなさいじゃすまされないよ」と怒っていた。
裸にされて振り回されることに怒りを感じていたのだろう。
私は「とにかくおなかに詰まっている水と便を、これからとるからもう少しがんばって」と言うしかなかった。手術ということばは使わないようにしたが、執刀のO医師も同じ考えだった。母はとにかく苦しいからなんとかして欲しいという気持ちだった。
「じゃ、早くして、早く…」と懇願するようになった。
よほど苦しかったのだろう。前日には、つぶやくように何かを言っていたのをそこにいた妹が、母の口元に耳をあてて聞いた。
「しにたい…」
妹はそれを「いたいの?」と聞き返したが母は首を振った。そのことがまた繰り返されそうだった。
その日は私が、母の口元に耳をつけるとはっきりと「死にたい」と言った。「死にたいのね」と私が応じ、母は頷いた。
あれほど強く、「痛い」も「死にたい」も口にしなかった人が苦しさにもがきながらかすかにつぶやいたことばであった。そしてそのあと何回も「早くして…」と言いながら、手術室のほうへ移動していった。その手を握るとギュッと握り返して来た。その力は残っていた。
私たちは大きな賭けをやろうとしていた。
手術は、手伝いの医師が4時にならないと来れないということで、2時過ぎからの予定が4時になり、4時半頃に執刀が開始された。付き添いの可否を医師に聞くと「いったんは引き取ってください。仮に危なくなって電話して集まったとしてもそのときはもう手遅れです。そうならないようにしますから」という答えが返ってきた。ということは、手術後、夜にでも電話があったら、それは死を意味するということなのだ。
6時か6時半頃だったろうか、看護師が私たち4人に「手術室に来てください」と言う。なにごとかと駆けつけると、身内のふたり、私と妹のみが手術着と帽子を着け、部屋の中に入るよう促された。
そこで見たものは、母の腹の上にさらけ出された腸の山であった。そのひとつは、大きな腸の袋と袋がパンパンに張っていて、その真ん中が“ゴムひも”状のものでぐるぐる巻きにとめてあるようなものだった。腸閉塞だった。完全に詰まっていた。その下のほうはよじれによじれていたものを直した状態にしたという説明であった。風船がしぼんでしまったようなくしゃくしゃになったようなものもあった。
よくこれで生きていた。苦しかったに違いない。なぜこの状態をもっと早く見つけることができなかったのか…そういう思いがさっと脳裏をかすめた。
腸に管(くだ)はもってきたこと、前述の“ゴム”のグルグル巻きのところは、切ってつなげるということが手術前の話などから想像できた。
手術が終わったのは何時頃だったろうか。よく思い出せない。ただその説明だけは鮮明に覚えている。
“ゴム”のグルグル巻きのところは切ってつなげ、パイプも小腸までもってきたので、もしここに水や便がたまったとしても取り除ける、ということであった。問題は、腸壁が大腸に癒着して大きく変形した部位をはがした際に、そこが破れた、というか亀裂があり、そこも縫合したけれど急に血圧が30ぐらいに下がって危険な状態になってしまったので、急いで手術を終えてお腹をふさいだ、という点であった。先生の説明では最後の最後になって危険が迫ってきた、もう少し時間があれば…と言うようなニュアンスで残念そうな表情も見せた。その表情が気にはなったが、ともかくも手術は終わり、まだその時点では母は生きていた。
私と妹は母の耳元で「よくがんばったね…よくがんばった」と言い、だらんとした手を握ってやったが、その握り返しはなかった。
腸を見せられた時、まだ母の体内にある内蔵のいくつかのかたまりはブルン、ブルンと呼吸にあわせて動いていた。
生きている…
まだ母の体の中では心臓が動き、他の臓器も動いていた。なんとかそのままもって欲しいと思った。そうして私たちは恐怖の電話の呼び出しがないことを望みつつ家に帰り眠った。
夜中の2時頃であろうか。ぐっすり眠っているところに携帯の振動と音が鳴って私はすぐに飛び起きた。死の知らせではなかった。しかしすぐに医院に来るようにとのこと。私たちは真夜中の高速を吹っ飛ばし、インターを降りてまもなくクリニックに着いた。すぐにナースステーション横の病室に案内されると、O先生も眠そうな顔つきでそこに来た。今はすこしもち直しているが、何回かは危ない状態になり、それが続いているとのこと。そうして説明しているうちにもまた血圧が下がり脈拍が少なくなってきた。そして心臓マッサージ。これをなん回も繰り返してきたらしい。
そして3時36分。母は息をひきとった。
O医師は「こういう結果になって申しわけありません」と言い、深々と頭を下げた。そのあとは看護師ふたりが、遺体をきれいにするので少し時間をくださいと言ってきた。葬儀社に電話をしてすぐに引き取りに来るよう指示された。クリニックには遺体安置室がなく、そういうことになっているらしい。そうするしかない…これには面食らったが、そうするしかないと思った。
しかし葬儀社に電話をすると、真夜中にも関わらずすぐに対応してくれ、時間を確認し、また先方から電話することが決まった。私たちは真夜中の待合室でじっと待った。
時おり、2人の看護師がトイレにバケツのようなものを運んだり、大きな布のかたまりを運ぶのが見えた。その間に葬儀社が1時間後に遺体を引き取りに来ることが決まり、搬送先もS市の実家と決まった。
40分か1時間くらい経っただろうか。看護師に呼び出され、私たちは病室に向かった。母の死に化粧は完璧と言ってもいいくらいに美しいものだった。手術後は見開き放しだった眼も閉じられ、全体が安らかな顔をしている。頰紅がうっすらとひいてあり、まるでまだ生きて呼吸をしているようだった。口紅もいい色だった。私たちはその表情と、化粧とはいえそのできばえに驚き、少し安心した。
それにしてもあっけなかった。
手術の最後が少しドタバタしたとしても、またよくなって数ヶ月、あるいはもっと生きられるだろうという思いがあった。あの強さ、気力、しっかりした対応からすると、手術もなんとか乗りきるだろうという思いこみがあった。だから、どうしてこんな簡単に死が訪れるのか理解しがたかった。しかし、そんな思い込みには関係なく、死は厳然とそこにある。
死に化粧の安らかさとふくらみも手伝い、やるだけのことはやった、しかし87歳の体はちょっともたなかった、母は安らかに死んだ、そういう思いが押し寄せてきた。
若いほうの看護師に「ほんとうに母はきれいになった。まるで生きているような表情、ありがとうございます」と言ったら、彼女はうれしそうに笑った。先生が「力足らずですみません」と言ったので、私は「可能性に賭けてくれたことは感謝します」と言葉を返した。現状を打開しようとする気概にあふれた若い先生だった。説明もはっきりしていて納得できた。この先生にもっと前に行き着いていたら、母の容体も変わっていたかもしれない。
一番はじめのA病院の内科医のつっけんどんな態度と、パーキンソン病とともに進行していた病を見抜けなかった無能さに怒りのようなものが湧いてきた。母は数年前にこの病院で、結腸にできた悪性腫瘍除去の開腹手術をしたが、それが後に腸の癒着を呼び込むことになった。結果論ではあるがパーキンソン病の専門棟をもつ2番目の病院にもっと早く移り、腸閉塞を見抜いてもっと早くこのOクリニックに来ていたら違った可能性もあり得た……すべてはあとのまつりである。
しかし最後の最後でこの状態をなんとかしようとする先生に出会ったことは不幸中の幸いなのかもしれない。あのまま、手術をしないで苦しみのなかで死んでいたら…お腹がパンパンに張ったまま、死んでいたらどうなっていたのだろうか?便は胃まで入ってきていた。そのまま放っておけば口から出てくる、そのような状況での決定であった。体をきれいにして死んだ。そのことはできた。
そして可能性に賭けたこと、結果は残念なことになったが、先生や自分たちの決断は間違ってはいなかった。母は最後に苦しんだけど、そのなかでユーモアを忘れずに、ひとりで死に向かっていった。生きているときを思い出させるような安らかな表情の死に顔を見せてくれた。23日、24日と日が経つにつれ、細く変わってはしまったが、クリニックでの直後の死に化粧の表情が、そこにいたものすべてに一種の安堵のようなものをもたらしたのは確かだった。
母の病院での2年半は、それなりに充実したものであった。親しい友人を得て会話をし、リハビリを繰り返しながら活発になり生き生きしていた。これを晩年と言うなら、晩年はどこか向こうの世界に行ってしまったひとのような、あるいは子どものような、不思議な雰囲気を漂わせ、憎めない存在になっていた。なによりユーモアがあった。リハビリのお姉さんとも信頼関係を築き、母が「この人、私のケライ(家来)なの」と笑って言うと、そのひとも「そうなの、私カズさんのケライなのよう!」と笑って返した。そういう冗談をふたりでよく言っていたのであろう。そんな関係をどこでも築いていった。
最初のA病院でのTさんとの関係は、病室での最初の他者との深いつながりであった。「あの人、京大を出ているけど何も知らないの」という母に対して、Tさんは「カズさんは何でも知っていて話をしていてほんとうに楽しい」と言っていた。もちろんこれは別々にこちらに言ったことで、母のことばは、直接Tさんに向けられたものではない。
また最初のA病院からB病院への転院の際に、看護師さん全員でやってくれた早めの誕生会も忘れられないものになった。「こんなにみんなと仲よくなって、別れを惜しまれた患者もいないだろう」と看護師のひとりが言っていた。母は病室がナースステーションに近いこともあり、働く彼女らとよくコミュニケーションをとっていた。Yさんをはじめとして、A病院の看護師らは先生と違ってしっかりしていた。医者は無責任で無能だった。しかし神経内科のN先生だけは、パーキンソン病をよく見定め、的確な処方をした。この処方は次の転院先のB病院でも踏襲された。
そのB病院の看護師長は最初こそ感じが悪い印象だったが、慣れてくるにつれて親身になって相談にのってくれた。
病院に入ったら、どこでも患者は人格を見られ、“品定め”をされるような気がしてならない。特にパーキンソン病のような特定疾患の場合は、認知症が進んでいることが多いので、そこに入ったら、そこの看護の流れに任せるしかない。排泄の世話が必要な場合は、一定時刻におむつの取り替えがあり、みんなが集まる食事の時間があり、そのあとは部屋に戻って眠る、という看護パターンが定着している印象を受けた。看護師たちはそれをてきぱきとこなし、見た目は明るく振る舞っていた。
母はそのなかにあって、自分が若い頃看護師だったことを打ち明けて彼女らと仲よくなった。話がおもしろいので彼女たちも頻繁に声をかけるようになった。そして冗談も言い合う。そういう関係がどこへ行っても築けていた。これは見事というしかない。
晩年というのは、そのひとの大きさや豊かさが試される時期なのだ。死に際してはその存在そのものが試される。死は人生の最も大きな最後の仕事であろう。母はこれを実行し、それに触れたみんなに深い印象を残した。こんなに母が豊かで深いものをもっていたとは…もしかするとそれは病気のなかで母が獲得したものかもしれない。
ひとり暮らしのなか、治療と介護が始まったはじめの頃は何ともなかったが、入院前のあたりでは目も輝きを失っていた。ところが入院して人と人とのつながりを得て俄然、生き生きとしてきた。もともと社交性はあったから、周りに人がいることが程よい刺激になったのだろう。細かいこと、余計なことを捨て去って自分のことに集中できるようになった。それは父の死のあとに母が言った言葉にも表れている。
「ようやくひとりになったから、これからはやりたいことをやる」
それは宣言だった。
若いときのかけがえのない時間を戦争に奪われ、いつも「もっと勉強したかった」が口癖だった。大人になって4人の子どもを育てるなかでは、みんなが寝静まったあとに訪れる自分の時間を、なにより大事にして和歌や随筆の時間に費やした。そして子どもたちが巣立ち、父の介護の何年かを献身的に尽くしたあとにやっと手に入れた自由の時間であった。だからこのことばはただのエゴではない。配慮と献身に明け暮れた人生の果てにやっとつかんだ、自分をとりもどす悲痛な叫びだった。
うぐいすが鳴いた時の「それどころじゃない…」ということばもそうした意味を含んでいた。あとの世界はどうなるのか?それどころじゃない。
母は自尊心をもったひとりの人間として死んでいったのである。
B病院の病室で、同室のTさんと童謡を大声で歌っていて、看護師に注意されたことがあった。パーキンソン病のひとは声が出にくくなるので歌うのがいいと先生も奨励していた。Tさんは楽しそうにそのことを話してくれた。そのとき、ふたりの頭のなかには、楽しく過ごした少女時代の自分の姿がかけめぐっていたのだろう。その歌声と想像の姿はたしかに存在した。回想としてではなく、生きた実在としてその姿のすべてがあった。だからこそ、あの晩年のなんとも言いようのないチャーミングな笑顔があった。